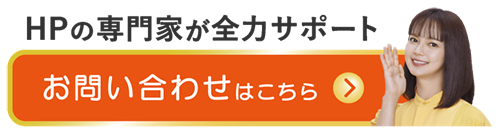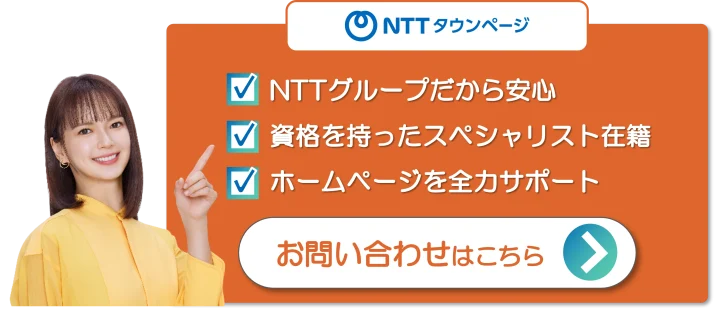更新日:2025年7月
オートバイ販売・修理業界は、近年、若年層の免許取得者数の回復やコロナ過における「三密」回避意識の高まりによる需要増加といった動きが見られました。しかし一方で、少子高齢化やEV二輪車の普及といった変化にも直面しています。
このような状況において、Webを活用した情報発信や顧客アプローチは、新規顧客獲得や既存顧客との関係強化に不可欠な要素となっています。本記事では、オートバイ販売・修理業界の最新動向戦略について、できる限りわかりやすく簡単に解説します。
オートバイ販売・修理の事業内容
それではまず、オートバイ販売・修理の事業内容について見ていきましょう。
事業内容
オートバイ販売・修理の主な事業内容は、大きく3つの分野に分かれます。
- 新車・中古車販売
- 修理点検・整備
- パーツ部品・アクセサリー用品販売
新車・中古車販売は、オートバイ販売業の根幹をなしていて、国内大手メーカーであるホンダ、ヤマハ発動機、スズキ、川崎重工業の製品はもちろん、世界中の多様なメーカーの二輪車を取り扱っています。お客さま一人ひとりの希望に沿った幅広い選択肢を提供し、理想のバイク探しをサポートする仕事です。
次に修理点検・整備の分野は、バイクが安全かつ快適に走行するために不可欠なサービスです。専門的な知識と技術を持つ専門スタッフが、定期的な点検から予期せぬ故障への対応、さらには性能を最大限に引き出すための高度な整備まで、多岐にわたるサービスを提供し、バイクを常に最適な状態に保ちます。
最後にパーツ部品・アクセサリー用品販売は、バイクのカスタマイズや安全性を高める上で欠かせない要素です。純正部品から高性能なカスタムパーツ、さらにはヘルメットやライディングウェアといった各種アクセサリーまで、豊富な品揃えでバイクライフをより豊かに彩る提案をしています。
オートバイ販売・修理の事業は、地域に密着したバイクショップ、特定のメーカーに特化した専門店、幅広い品揃えが魅力のバイクパーツ&用品販売店、気軽にバイクを楽しめるレンタルバイク店、そして専門的な技術でメンテナンスを担うバイク専門の整備工場といったさまざまな形態で展開されており、お客さまの多様なニーズに応える体制が整っています。
オートバイ販売・修理の市場規模
経済産業省によると、二輪車・バイク業界の市場規模は徐々に縮小していて、2024年の販売台数は40万台を下回りました。新型コロナウイルス感染症が流行した2021~2023年頃、感染予防対策として「三密」を避けられる移動手段としての二輪車の需要が一時的に増加しましたが、その需要も落ち着き、2024年には元の水準に戻っています。
販売台数のピーク時と比較すると約10分の1まで減少しているため、この現象をどこまで抑えられるかが大きな課題と言えます。
参照:経済産業省「⼆輪⾞産業の概況」
オートバイ販売・修理の利用者の年齢層と販売額
オートバイ販売・修理の利用者の年齢層
オートバイなどの二輪車購入者の年齢構成については、経済産業省によると、40~50代の割合が年々増加しています。2023年度の購入者の平均年齢は55.5歳であり、40代以下の割合は全体の26%のみとなっています。
利用者の年齢層が高いため、今後安定的な需要を確保するためにも20~30代などの若い層にもアプローチできるような施策が求められています。例えば、Web上の写真と販売店の実車のみで情報発信をするのではなく、SNSの活用やバイク専門誌での発信など、多様な発信方法を検討するようにしましょう。
参照:経済産業省「⼆輪⾞産業の概況」
オートバイ販売・修理の販売金額
オートバイを購入する際にかかる費用としては、オートバイの代金、自賠責保険の保険料や税金などの法定費用、そして納車費用や手数料などの諸費用があります。これは最低限の費用で、この3つに加えて任意で入る保険の代金や、ヘルメットやグローブなどのアクセサリー用品も必要です。
特に変動が大きいのはオートバイの車体代で、当然バイクの大きさやスペックによって費用は大きく異なります。費用が高くなればなるほど、購入までのプロセスが慎重になる人も多いので、丁寧なサポートが必要だと言えます。
オートバイ販売・修理の課題と今後
ここからは、オートバイ販売・修理業界の課題と今後について見ていきましょう。
オートバイ販売・修理業界の課題
オートバイの利用者構造についての説明でも触れましたが、ユーザーの高齢化と若年層のバイク離れは業界の大きな課題と言えます。
若年層でも移動手段として原付バイクを利用する人は一定数いますが、「趣味や娯楽」としてバイクを所有する若者は年々減少しており、特に小型二輪以上の排気量のバイクは車検費用を含めた維持費の高さが購入の妨げとなっています。
また、オートバイを動かすことで発生する排気ガスも環境問題に影響を及ぼすので、この排出ガスの削減も課題の一つです。
環境問題への対策として「令和2年排ガス規制」が発表されましたが、排出ガスを浄化する装置の劣化を監視する機能である車載式故障診断装置(OBDⅡ)の搭載が義務化されたことで生産コストが上がり、販売額の高騰という新たな課題も生まれています。
参照:国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正」
オートバイ販売・修理業界の将来性
環境問題への影響や、若者のバイク離れなどから業界課題は尽きないですが、その中でも環境問題への影響を抑える電気二輪車の開発は注目されています。
電気二輪車とは、電気モーターと充電式バッテリーを動力源としている二輪車で、ガソリンを燃料としていないので、排出ガスの削減に貢献できる環境にやさしいモデルです。国によっては電気二輪車の研究に補助金を提供している場所もあり、日本国内だけでなく、世界のオートバイ市場でトレンドとなっていく可能性があります。
また、移動手段としてではなく、キャンプなどのレジャー目的や運動のためにバイクを楽しむ層が増えたことも、市場にややプラスの影響を与えていると言えます。このような多角的な要因が絡み合い、世界の二輪車市場は今後も力強い発展が期待されています。
ホームページ制作・運用サービスWebサービスのおすすめはデジタルリード
オートバイ販売・修理の方がホームページを作成する際には、集客のためのさまざまなポイントや、オンラインショップの導入など、自分たちで対応するのはなかなか大変なことが多くあります。しかしながら、ホームページの作成を外部に委託するといっても、どこに頼めばいいのかわからない、ホームページを作った後の運用にも不安があるなど難しい面もあるかと思います。
NTTタウンページでは、ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」をご提供しています。
2019年のサービス提供開始以降、累計45,000件を超えるホームページを制作・運用し、個人事業主、中堅・中小企業をはじめとした多くのビジネスオーナーさまにご利用いただいてきました(2025年3月現在)。
これまで培ってきたNTTグループの知見とノウハウを活かして、多種多様なサービスと充実のサポート体制で、オートバイ販売・修理業界のみなさまのホームページ制作から公開後の運用に至るまで、責任を持ってサポートいたします。
ホームページは"制作して終わり"ではなく、その後の集客など、目的の「成果」につなげてこそ価値があります。
「インターネット・Webが苦手なのでサポートしてほしい…」
「競合に”勝てる”ホームページをめざしたい」
など、当社はホームページ活用に関するお悩み・課題にも寄り添いお支えします。
ぜひ、あなたのホームページの全てをお任せください!
オートバイ販売・修理のホームページデザイン例・業界動向に関連する記事