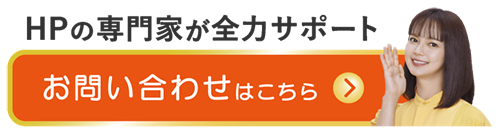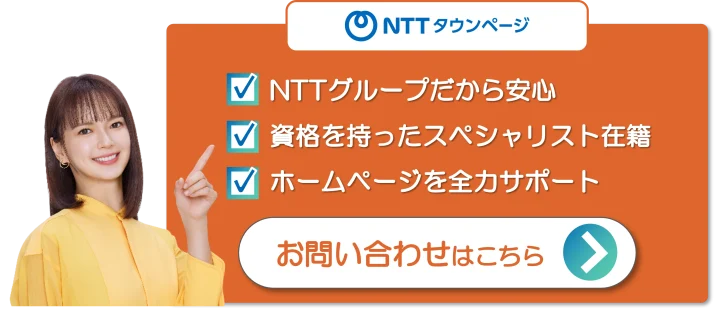最終更新:2025年6月
近年、訪日外国人が増加し、インバウンド市場は拡大の一途をたどっています。「インバウンド需要を取り込むために、何か対策を取りたいと思っても具体的に何をしたらいいのかわからない…。」そんなお悩みを抱えているビジネスオーナーさまも多いのではないでしょうか。
この記事では、インバウンド集客の重要性と具体的な方法について詳しく解説します。せっかくのビジネスチャンスを逃さないためにぜひ参考にしてください。
● 中小企業の方、個人事業主さま必見!お役立ち資料無料ダウンロード

デジタルマーケティング手法が丸わかり!あなたの店舗・企業の集客に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます
今インバウンド集客に注力したほうが良い2つの理由
まず初めに、なぜ今インバウンド集客に注力すべきなのか、その理由について解説します。
訪日外国人数が増加し続けているため
インターネットやテレビから流れてくる情報などで、インバウンドが増加していることはご存知の方が多いと思います。では、ここで訪日外国人数の推移について実際の数字を見ていきましょう。
日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」によると、2024年の訪日外国人数は、36,870,148人となり、2023年の25,066,350人から、47.1%の伸率となりました。更に、2025年4月の訪日外客数は 3,908,900 人で、前年同月比では 28.5%増となっています。これは、過去最高だった2025年1月の 3,781,629 人を上回って単月過去最高の記録となり、単月として初めて390万人を突破しました。
参考:
訪日外客統計 国籍/月別 訪日外客数(2003年~2025年)(Excel)|JNTO(日本政府観光局)
訪日外客数(2025年4月推計値)|JNTO(日本政府観光局)
訪日外国人の旅行支出額が増加しているため
では次に、訪日外国人の旅行支出額について見てみましょう。
国土交通省観光庁「訪日外国人の消費動向」によると、2024年の訪日外国人旅行消費額は総額で8兆1,257億円と推計されています。2023年は5兆3,065億円だったため、53.1%増となりました。費目別にみると、宿泊費が33.6%、買物代が29.5%、飲食費が21.5%を占めています。また、一般客1人当たり旅行支出額は、22.7万円となっています。
日本政府はこの状況に対して、「2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円を達成する」という目標を掲げているため、今後もインバウンド需要の増加は続くものと思われます。このため、インバウンド集客は今後のビジネスの成長にとって重要なカギになることが予測されるのです。
参考:「訪日外国人の消費動向」2024年度版|国土交通省観光庁
「訪日外国人の消費動向」2023年度版|国土交通省観光庁
観光立国推進基本計画(第4次)について|国土交通省観光庁
インバウンド集客に役立つホームページを作るための事前準備
近年では、旅行の情報取集手段として、インターネットを利用した検索やSNSが利用されることが多くなりました。このため、インバウンド集客においても、世界中どこからでも見ることができるホームページの存在が重要となるのです。
ここからは、増加し続けるインバウンド需要を逃すことなくビジネスチャンスにつなげるために、インバウンド集客に役立つホームページを作る際に必要な事前の準備について解説します。
ターゲットの設定
インバウンド集客に役立つホームページを作るうえで、ターゲットを明確に設定することはとても重要なことです。
自社のサービス・商品を利用してくれるお客さま(ペルソナ)はどんな層なのかをできるだけ明確に設定しておくと、その後のサイト制作もブレることなくスムーズに進めることができます。ターゲットが複数いる場合は複数設定しても構いませんので、年齢、性別、職業、家族構成、国籍など、できるだけ具体的なターゲットのイメージを作り上げておきましょう。
【ペルソナの例①】
年齢:30歳
性別:女性
職業:IT企業勤務
家族構成:独身(両親、兄と同居)
国籍:中国
訪日の目的:友人との女子旅(3泊4日)
関心:SNS映え、日本食、ショッピング
【ペルソナの例②】
年齢:52歳
性別:男性
職業:営業マネージャー(製造業)
家族構成:妻(50歳・パートタイムの事務職)、息子(17歳・高校生)、娘(14歳・中学生)
国籍:アメリカ
訪日の目的:家族での文化体験を兼ねた観光旅行(10日間)
関心:歴史的建造物や寺社仏閣の見学、日本の伝統文化体験、家族で楽しめる自然体験
訪日外国人の動向・トレンド調査
インバウンド集客をするためには、訪日外国人の動向や、トレンドについても調べておく必要があります。日本政府観光局(JNTO)が公表している「訪日外客統計」や国土交通省観光庁が公表している「インバウンド消費動向調査」などで訪日外国人の動向やトレンドについて確認しておきましょう。
また、「訪日ラボ」のようなインバウンド需要情報を配信するサイトからも情報を得たり、SNSで最新のトレンドをチェックしてみたりするのもよいでしょう。
参考:訪日外客統計|JNTO(日本政府観光局)
インバウンド消費動向調査(旧 訪日外国人消費動向調査) | 観光統計・白書 | 国土交通省観光庁
ホームページを活用したインバウンド集客の具体的な5つの方法
それでは、ここからはホームページを活用したインバウンド集客の具体的な方法について、代表的なものを5つご紹介します。
ホームページを多言語化する
今や、訪日外国人の多くは、日本を訪れる前や、訪れている最中にインターネットで検索して情報を入手するのが当たり前になっています。このため、検索した結果たどり着くホームページにどれだけ旅行客にとって有益な情報が載っているかで差がつきます。
日本を訪れようとしている外国人がせっかくあなたの会社のホームページにたどり着いても、日本語にしか対応していなければ十分なアピールができません。そこで、ターゲットに合わせた言語設定をしておくことで、自社の商品やサービスの魅力を十分に伝えることができるようになるのです。
【関連記事】
ホームページの多言語化の方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ホームページを多言語化する5ステップ!切り替え形式や注意点も
Googleビジネスプロフィールの情報を充実させる
Googleビジネスプロフィール(GBP)は、Google検索やGoogleマップ上に、自社のビジネス情報を無料で掲載、管理ができる強力なツールです。
このGoogleビジネスプロフィールへの必要項目の登録を確実に行って、プロフィール情報を充実させることで検索画面で上位に表示されやすくなると言われているため、とても重要となります。
さらに投稿機能で最新情報を発信したり、レビューに迅速かつ丁寧に返信することで信頼性を高めることも可能です。Google マップで上位表示されれば地図検索で目にとまりやすくなり、外国人観光客にもアピールしやすくなるでしょう。
【関連記事】
Googleビジネスプロフィールを活用した集客方法は、以下の記事も参考にしてみてください。
Googleマップ(グーグルマップ)を使った集客について
デジタルリードでは、Googleビジネスプロフィール登録・運用代行サービスも行っています。詳細について気になる方は、以下のボタンからチェックしてください。
外国人観光客向けのサイトに情報を掲載する
インバウンド集客においては、外国人観光客向けのポータルサイトの活用も有効です。外国人観光客向けのポータルサイトは、ホテル・旅館だけではなく観光名所やレストランなどの情報も掲載されているため、訪日外国人観光客の多くが情報収集に利用しています。
このため、自社の情報を掲載することで、外国人観光客の目に触れる機会が増えて認知度向上につながり、そこからの高い集客効果が期待できるのです。
海外向けの口コミサイトに投稿する
インバウンド集客を行う際には、海外向けの口コミサイトへの投稿や連携も効果的な手段です。多くの外国人旅行者が信頼する口コミサイトに施設や店舗の情報を投稿することで、外国人旅行者からの評価を獲得しやすくなります。実際に利用した人の口コミはユーザーが信頼を寄せやすいコンテンツのため、多くの外国人旅行者からの口コミを獲得することでプロモーション効果が期待できます。
ただし、投稿数が増えると批判的な意見が含まれる場合もあります。口コミの内容をもとにサービスの改善を図り、評価の向上につなげる努力も必要です。口コミサイトを活用してインバウンド集客を行うには、質の高いサービスを提供し続け、満足度を維持していくことが求められます。
海外向けのSEO対策をする
インバウンド集客においてもSEO対策は重要となりますが、このSEO対策も日本国内向けと海外向けでは違いが出てきます。
日本でよく使われる検索エンジンは、GoogleやYahoo!が代表的ですが、国によってはその他の検索エンジンが主流である可能性もあります。そのため、各国で使われている検索エンジンに適したSEO対策が必要になります。ターゲットとなる国で主流となる検索エンジンを確認し、それに対応したSEO対策を行いましょう。
また、国ごとの言語に応じた適切なキーワード設定やメタタグの最適化も重要です。同じ商品やサービスでも、地域ごとに異なる検索意図を持つユーザーが多いため、現地の検索トレンドを把握することが必要となります。
ホームページ以外にもSNSを活用した集客方法もある!
SNSは現代人にとって今や欠かせないツールであり、海外からの旅行客の多くも情報取集の手段としてSNSを利用しています。このため、インバウンド集客においてもSNSの活用は非常に効果的な手段となっています。
画像や動画を通じて直感的に情報を得られることや、リアルタイムの情報が入手できることがSNSの魅力です。また、SNSはユーザー間での情報の拡散が容易なため、魅力的なコンテンツを投稿し、ユーザーがそれをシェアすることで、自然な形で情報が拡散されていきます。
そして、SNSのもう一つの魅力が、実際に日本を訪れた外国人観光客による口コミ効果です。例えば、日本の観光地で撮影した魅力的な写真をSNSに投稿し、それを友人や家族にシェアすることで、潜在的な訪日外国人観光客の興味を引き、自分もそこに行ってみたいと思ってもらえるきっかけになるかもしれません。
インバウンド集客のためのホームページ制作における注意点
インバウンド集客を意識したホームページを制作する際には、注意しなければならないポイントもあります。ここからは、インバウンド集客のためのホームページ制作における注意点をご紹介します。
外国語でのコミュニケーションを意識したページ設計が求められる
インバウンド集客を意識したホームページを制作するうえで大切なのは、「外国語に対応する」こと以上に、「外国語話者に伝わる」ことです。単に今あるホームページを翻訳機で英語や中国語に直訳しただけでは外国人にうまくアピールできないため、外国語でのコミュニケーションを意識したページ設計が必要です。
それに加えて、言語切り替えボタンを目立つ位置に配置したり、写真やイラスト、ピクトグラム※を活用することで言語に依存せずに情報を伝えるなど、外国人ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるような工夫も必要になります。
※ピクトグラム:特定の言語を使わずに情報を視覚的に伝えるためのシンプルな図形や記号のこと
国内の顧客離れを防ぐ配慮も必要になる
インバウンド集客を意識して外国人向けの情報発信に力を入れるあまり、国内の顧客への対応がおろそかになると、既存顧客の足が遠のいてしまう可能性もあります。
外国人観光客への配慮と同時に、国内顧客への敬意と継続的な価値提供も忘れないようにしましょう。
文化圏ごとの慣習の違いを理解したデザイン・表現を意識する
インバウンド集客を意識したホームページを作る際には、デザインや表現にも注意が必要です。
たとえば、デザインに使う色は、ターゲットとする国の文化圏での意味合いを理解したうえで選ぶ必要があります。一例をあげると、日本では「白」は清潔や神聖さを表す色ですが、中国では「白」は喪を連想させる色として避けられることがあります。
また、写真やイラストの選定にも注意が必要です。肌の露出や宗教的なシンボルが含まれる画像は、特定の文化圏では不快感を与える可能性があります。
このように、文化的な背景が異なれば、同じ表現でも受け取り方が大きく変わることがあります。ターゲット層となる国の文化や習慣を事前に確認し、配慮を欠くことがないように注意しましょう。
インバウンド市場の拡大は、今まさに多くのビジネスにとって大きなチャンスとなっています。しかし、その波に乗るためには、ただ外国人観光客を「迎える」だけではなく、「理解し、伝える」ための工夫が欠かせません。
「何から始めればいいのかわからない」と思っていた方も、この記事をきっかけにできることから一つずつ始めてみてはいかがでしょうか。インバウンド需要の拡大というビジネスチャンスを逃さないために、ホームページを活用したインバウンド集客を始めましょう!
● 中小企業の方、個人事業主さま必見!お役立ち資料無料ダウンロード

デジタルマーケティング手法が丸わかり!あなたの店舗・企業の集客に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます
NTTタウンページでは、ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」をご提供しています。
2019年のサービス提供開始以降、累計45,000件を超えるホームページを制作・運用し、個人事業主、中堅・中小企業をはじめとした多くのビジネスオーナーさまにご利用いただいてきました(2025年3月現在)。
これまで培ってきたNTTグループの知見とノウハウを活かして、多種多様なサービスと充実のサポート体制で、忙しいビジネスオーナーさまのホームページ制作から公開後の運用に至るまで、責任を持ってサポートいたします。

ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」の特長
特長①
ホームページ制作・運用はNTTグループの専門スタッフがフルサポート!
特長②
さまざまな目的のホームぺージ制作に対応、デザインも洗練!
特長③
ネットショップ・予約機能など、ホームページでの成約に導く充実機能多数!
ホームページは"制作して終わり"ではなく、その後の集客や売上アップなど目的の「成果」につなげてこそ価値があります!
「インターネット・Webが苦手なのでサポートしてほしい…」
「競合に”勝てる”ホームページをめざしたい」
など、当社は全てのビジネスオーナーさまのホームページ活用に関するお悩み・課題に寄り添い支えます。
ぜひ、あなたのホームページの全てをお任せください!
この記事の著者

NTTタウンページ Webマーケティングチーム
全員がウェブ解析士資格取得。同社にてWebマーケティングの他、ホームページ制作・営業・CSM(カスタマーサクセスマネジメント)など、幅広い業務経験を積んだメンバーにより構成され、ビジネスオーナーさまのホームページ制作・運用やWebマーケティングに役立つ情報を発信しています。
※Googleビジネスプロフィール、Google、Googleマップは、Google LLCの登録商標または商標です。
※Yahoo!は、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。
※その他本記事に記載されている会社名、製品名、サービス名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。
ホームページからの集客基礎知識に関連する記事