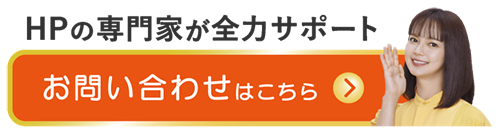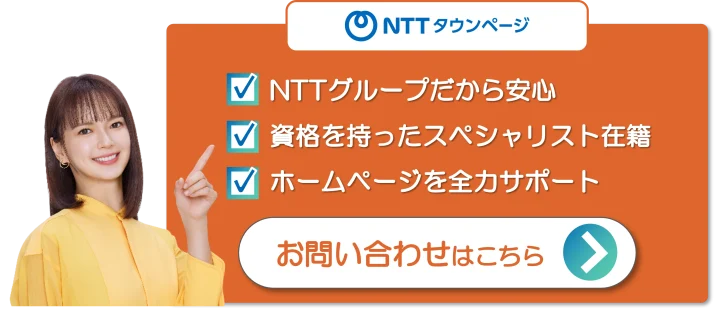最終更新:2025年7月
ホームページに掲載されるコンテンツには、一定の品質基準があります。その基準に満たしていないと、いくら新しいコンテンツを作成しても、検索エンジンに低品質なコンテンツを発信しているホームページであると悪い評価を付けられてしまう可能性もあるのです。
この記事では、「低品質コンテンツ」と判断されやすい要素や、既存のコンテンツの品質を高める方法について解説します。
ホームページを公開しても、「なぜか思ったように検索順位が上がらない」「何を改善すれば良いのかわからない」と困っているホームページ運用担当の方は、この記事を読んでコンテンツの質を上げる方法を習得しましょう。
● 中小企業の方、個人事業主さま必見!お役立ち資料無料ダウンロード

デジタルマーケティング手法が丸わかり!あなたの店舗・企業の集客に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます
そもそも低品質コンテンツとは? 3パターンで紹介
まずは検索エンジンに低品質なコンテンツだと判断されやすい要素について、3パターンに分けて紹介します。どれか一つでも当てはまっているものがあれば改善対象なので、自社のホームページを見ながら確認しましょう。
コンテンツ内容がユーザーに悪影響を与えているもの
コンテンツの品質基準はいくつかありますが、前提として閲覧したユーザーを不快にさせたり傷つけたりする可能性があるコンテンツは、高い確率で低品質だと判断されるでしょう。例えば、特定のバックグラウンドを持つ人に対して侮辱するようなコンテンツや、過激で差別的な伝え方をしているコンテンツなどが当てはまります。
企業のホームページ上でこのような表現が用いられることは少ないかもしれませんが、無意識的に差別表現を使用している可能性もあります。Googleが発表しているコンテンツポリシーを参考にして、もし「不適切なコンテンツ」に一つでも当てはまる表現がある場合は、即座に非公開対応をして表現を見直しましょう。
コンテンツ内容が低品質なもの
伝え方という観点ではなく、単純にコンテンツの内容自体が薄いものも低品質なコンテンツと判断されやすいと言えます。
普段検索エンジンで何かを調べるときに、タイトルに惹かれてクリックしても、内容が想像していたより薄くて疑問が解決しなかったという経験がある人も多いのではないでしょうか。このように、訪問したユーザーのニーズに適切に応えられないような内容だと、コンテンツ内容自体の品質が低いと判断される可能性が高いのです。
コピー&ペースト記事や誘導ページなどの意図的に流入を稼ごうとするもの
企業としての利益を追求するためだけのコンテンツは、ユーザーのためにならないケースが多いので、場合によっては低品質だと判断されることがあります。
例えば、話題になっている記事のコピー&ペーストでホームページの流入数を稼ごうとしたり、引きの強いタイトルを使用してクリックをさせて、商品の誘導ページに無理やりつなげようとしたりなどが当てはまります。
特に他のホームページのコピーコンテンツはペナルティになる可能性が高いので、PV数稼ぎを一番に考えたようなコンテンツは避けるようにしましょう。
低品質コンテンツがメディアに与える影響
ホームページには多くのコンテンツが掲載されているため、少しくらい低品質なコンテンツがあっても問題ないのではと考えている方もいるかもしれません。
しかし低品質コンテンツがホームページに与える影響は、軽視して良いものではありません。どのようなリスクがあるのか、詳しく説明します。
メディア全体の評価や検索順位が下がる
ホームページ全体の中では低品質なコンテンツの割合が少なかったとしても、低品質なものを放置しているという事実があるため、メディア全体の評価が下がってしまう可能性があります。
コンテンツ単体の検索順位が上がらないのはもちろんのこと、今まで上位表示されていた検索キーワードでも、メディア全体の評価が下がれば順位は必然的に下がってしまいます。どれだけ良いコンテンツを後発で作成しても、足を引っ張られてしまう可能性があるため、低品質なコンテンツに当てはまるものは放置しないようにしましょう。
Googleからペナルティを受ける可能性が高まる
Googleのペナルティには2種類あり、手動ペナルティと自動ペナルティと呼ばれています。
手動ペナルティ
Googleが手動で課すペナルティのことです。目視で確認したうえで低品質なコンテンツや悪質な被リンクがないかを確認しているもので、もしペナルティとなった場合はGoogleサーチコンソールから警告があります。
自動ペナルティ
検索エンジンのアルゴリズムが自動で判別して課すペナルティのことです。手動ペナルティのように警告はないので、順位が下がってからでないとペナルティになったかどうかが判断できません。
どちらのペナルティでも、低品質なコンテンツが掲載されていないかは確認されているため、放置しているとペナルティを課されてホームページ全体の順位が下がったり、最悪の場合はインデックスから削除されたりする場合もあります。
すぐに「低品質」と判断するのも危険! 勘違いされやすい品質基準
低品質なコンテンツの危険性を改めて実感して、あれもこれもペナルティの危険性があるのではと焦っている人も中にはいるかもしれません。
しかし、すぐになんでも低品質だと判断するのも、またリスクになります。ここではよく勘違いされやすい品質基準を紹介するので、焦って低品質だと決めつけないように注意しましょう。
文字数が少ない
「文字数が少ない=コンテンツの内容が薄い」と考えている人も多いかもしれませんが、これは必ずしも成り立つわけではありません。
例えば、専門家によるQ&Aコンテンツは、端的な回答であれば文字数こそ少ないですが、内容は専門的で調べてもわからないようなものである可能性が高いでしょう。また、よくある質問のページも、ほかのページに比べれば文字数は少ないですが、ユーザーニーズを的確にとらえた重要なページです。
逆に考えれば、10,000字以上の記事コンテンツでも、でたらめな文章で何を伝えたいかがわからなければ低品質になりますよね。このように、文字数だけでは厳密な品質は判断できないので、そのコンテンツがどのようなニーズに対するアンサーとなっているかで判断をするようにしましょう。
直帰率が高い
直帰率とは、ホームページを訪れたユーザーが最初にアクセスしたページだけを閲覧して、サイトを回遊せずにホームページから離脱してしまった割合のことを指します。
一見すると、他のページを見てくれないということはマイナス評価のように感じられますが、実は高評価だからこそ直帰率が高いというケースもあります。
例えば、そのページのコンテンツだけでニーズが満たされたからこそ他のページを見る必要がなかったというケースです。ニーズがわかりやすいコンテンツであればあるほど、この可能性は高いと言えます。
そのため、直帰率の高いコンテンツのニーズを改めて分析して、マイナスなのかプラスなのかを判断することが重要です。
オーガニック検索での流入数が少ない
オーガニック(自然)検索で見られていないということは、検索画面上で品質の低さからクリックが少ないのではと考えてしまいがちですが、比較対象によっては品質が関係ない場合もあります。
オーガニック検索での流入数は、そのコンテンツが狙っているキーワードの検索ボリュームが大きく関係しています。検索ボリュームとは、キーワードをどれだけの人が検索しているかという指標なので、例えば検索ボリュームが10のキーワードと1000のキーワードの流入数を比較しても、ボリュームが大きい方のコンテンツが見られやすくなるのは当然ですよね。
このように単なる流入数だけを見ると品質を誤認してしまう可能性もあるので、検索ボリュームに対する流入数の多さで比較するようにしましょう。
低品質コンテンツを見極める2つの方法
ここからは実践編として、既存のコンテンツで低品質なものがないかを見極める方法を紹介します。今までツールを活用してこなかった方も、以下を読み見ながら一緒に確認しましょう。
Googleサーチコンソールでインデックスされていないページを確認する
Googleサーチコンソールでは、画面左側のメニュー「▼インデックス作成」の「ページ」から、ホームページ上のコンテンツのインデックス状況を確認することができます。
インデックスされていない記事にもいくつか種類があって、特に確認してほしいのは「クロール済み – インデックス未登録」というステータスになっているコンテンツです。これは、Google側がそのコンテンツを見たにもかかわらずインデックスしなかったという状態なので、何かインデックスするに値しない要素があったと考えられます。
インデックスしなかった要因が低品質だったからという可能性もあるので、「クロール済み – インデックス未登録」の記事が増えていないかは定期的に確認しましょう。
【関連記事】
Googleサーチコンソールの使い方は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
初心者でもわかる!Googleサーチコンソールの使い方マニュアル
Googleアナリティクスでページごとの流入数を確認する
先ほど「オーガニック検索の流入数が少ないコンテンツが必ずしも低品質ではない」と説明しましたが、急に流入数が大幅に下がったというケースは別です。
流入数の推移を見るためには、Googleアナリティクスのレポート機能を活用しましょう。左側のメニューの「エンゲージメント」の「ページとスクリーン」をクリックすると、ページごとのセッション数(流入数)がわかります。
もし大幅に下がっているものがあれば低品質コンテンツと判断されて順位が大きく下がった、あるいはインデックスが外されてしまったという可能性があるので、いくつかピックアップして内容を調べてみましょう。
公開済みの低品質コンテンツを改善する方法
すでに公開しているコンテンツで「低品質と判断されてしまうかもしれない」と感じたものがあった場合は、放置せずにそのコンテンツをどのように活かすかまで考えましょう。
該当するコンテンツの役割や品質間によって対応が変わるので、詳しく解説します。
記事の内容を活かす場合:リライトをして品質基準を上げる
コンテンツの内容が少し薄かったり、一部表現がわかりにくかったりする程度であれば、リライトをして高品質に引き上げる方法がおすすめです。元のコンテンツを活かした対応なので、1記事単位で見ればそこまで時間もかからないでしょう。
しかし、低品質コンテンツに該当するものが多くリライトが追い付かないというケースもあるかと思います。その場合は、他の対応も検討しながらホームページにおいて重要なページからリライトを進めるというように、優先順位を付けて対応を変えてみてください。
機能的にページを残したい場合:no index対応をする
no index対応をするとGoogleにクローリングされなくなるので、ペナルティなどのホームページの評価に影響することがなくなります。しかし同時に検索結果にも表示されなくなるため、ユーザーの流入は見込めなくなるので、no index対応は慎重に検討しましょう。
ページは残しておきたいけどまだリライトを進める準備ができていないという場合は、no index対応も選択肢の一つにしても良いかもしれません。
修正しても流入が見込めない場合:ページを削除する
リライトはあくまで元々のコンテンツを活かして高品質に引き上げる方法なので、全体を修正しなければいけない場合はリライトより削除したほうが良いケースもあります。例えば、元々のコンテンツが誰かを批判するような内容や差別的な考えに基づいているなどであれば、一から作り変える必要があるので、一度削除して新規作成したほうが良いと言えます。
また、流入数が0に等しく、削除してもホームページに影響がなさそうな場合は、リライトができるまで放置するよりも削除対応を進めたほうがホームページの評価が上がる可能性もあります。とはいえ、削除したものは戻せないので、慎重に判断したうえで対応を進めるようにしてください。
今後制作するコンテンツを高品質にするために意識したい3つのポイント
最後に、今後作成するコンテンツを低品質コンテンツにしないための方法を紹介します。これら3つを意識すれば、品質基準を守ったコンテンツ制作ができるので、今から体制を整えましょう。
E-E-A-Tに沿った内容で制作するという共通認識を持つ
英語版のGoogleの品質評価ガイドライン「General Guidelines」には、「E-E-A-T」という品質基準が記載されています。4つの評価基準からなる質の高いWebサイトに求められる要素で、具体的には以下のような内容です。
- Experience(経験)
- 実体験からくる疑問や不安の解消方法のような、具体的な内容がコンテンツに含まれている
- Expertise(専門性)
- 特定の分野やトピックに関して高い理解度や専門性がある
- Authoritativeness(権威性)
- 情報の正しさや客観的な根拠が明示されているか
- Trustworthiness(信頼性)
- Webサイト全体や運営者が信頼できて安全性が高いサイトである
この4要素を満たすようなコンテンツを作成することで、ホームページ全体の評価も高まっていきます。4つ目の「信頼性」はその他3つが満たされることで強固になるため、まずは情報の信頼性や具体性に関して、自社でできることを検討しましょう。
【関連記事】
E-E-A-Tの内容について、より詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめです。
E-A-TとE-E-A-Tの違いとSEOへの影響
コンテンツのキーワード選定により注力する
ホームページのコンテンツは、どのようなキーワードを想定して作るかどうかで方向性が大きく変わります。
例えば、記事コンテンツで考えると「ホームページ 作り方」と「ホームページ 制作会社」というキーワードがあるとします。どちらもホームページを作りたいというユーザー像が浮かびますが、前者だと自分で作成するパターンも含み、後者は制作会社に依頼するということが決まっているパターンが予想されます。このように、自社がどのような人をターゲットとするかで、細かくキーワードを設定しないと、ねらいたいターゲットにコンテンツが届かなくなってしまうのです。
今まで細かくキーワードを設定してこなかったという方は、まずはホームページにどのような人を呼び込みたいかという観点で、ペルソナを設定してキーワード選定を進めてみてください。
【関連記事】
キーワード選定の基本については、こちらの記事で解説しています。
デジタルマーケティングにおけるキーワード調査について
ユーザーを不快にさせる内容・表現へのチェック体制を強化する
コンテンツの大きな方向性にばかり目を配って、細かな表現面をおろそかにするのはもったいないので、表現や伝え方までしっかりこだわりましょう。特に、ユーザーによっては不快になるような表現や、一部に対する差別的な表現などは注意してください。
普段何気なく使っている言葉でも、あるバックグラウンドを持つ方にとっては差別的な表現になることもあります。インターネット上に公開されるということは、世界中の人に見られる可能性を考慮しなければならないので、誰が見ても不快にならないコンテンツをめざしましょう。
低品質コンテンツについて、基準や改善する方法について解説しました。ホームページ制作に力を入れているのになぜか評価がうまくついてこないという人も、この記事で紹介した基準を守ったコンテンツ制作を続ければ次第に評価もついてくるでしょう。
すでに公開されている低品質コンテンツなコンテンツについても、見ないふりをするのではなく、ホームページ全体として何が一番リスクがないかという観点で、適切な対応を検討してみてください。
もし、自社では適切な回答が出ない場合は、ぜひNTTタウンページにご相談ください。ホームページに関して専門知識を持ったスタッフが対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
● 中小企業の方、個人事業主さま必見!お役立ち資料無料ダウンロード

デジタルマーケティング手法が丸わかり!あなたの店舗・企業の集客に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます
NTTタウンページでは、ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」をご提供しています。
2019年のサービス提供開始以降、累計45,000件を超えるホームページを制作・運用し、個人事業主、中堅・中小企業をはじめとした多くのビジネスオーナーさまにご利用いただいてきました(2025年3月現在)。
これまで培ってきたNTTグループの知見とノウハウを活かして、多種多様なサービスと充実のサポート体制で、忙しいビジネスオーナーさまのホームページ制作から公開後の運用に至るまで、責任を持ってサポートいたします。

ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」の特長
特長①
ホームページ制作・運用はNTTグループの専門スタッフがフルサポート!
特長②
さまざまな目的のホームぺージ制作に対応、デザインも洗練!
特長③
ネットショップ・予約機能など、ホームページでの成約に導く充実機能多数!
ホームページは"制作して終わり"ではなく、その後の集客や売上アップなど目的の「成果」につなげてこそ価値があります!
「インターネット・Webが苦手なのでサポートしてほしい…」
「競合に”勝てる”ホームページをめざしたい」
など、当社は全てのビジネスオーナーさまのホームページ活用に関するお悩み・課題に寄り添い支えます。
ぜひ、あなたのホームページの全てをお任せください!
この記事の著者

NTTタウンページ Webマーケティングチーム
全員がウェブ解析士資格取得。同社にてWebマーケティングの他、ホームページ制作・営業・CSM(カスタマーサクセスマネジメント)など、幅広い業務経験を積んだメンバーにより構成され、ビジネスオーナーさまのホームページ制作・運用やWebマーケティングに役立つ情報を発信しています。
・Google、Googleサーチコンソール、Googleアナリティクスは、Google LLCの登録商標または商標です。
seo対策・検索対策の基礎知識に関連する記事