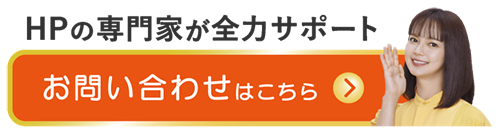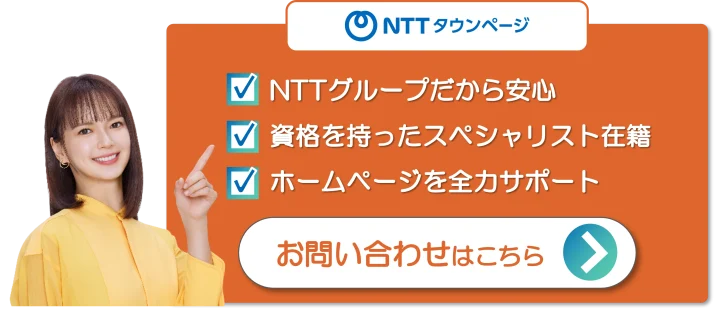最終更新:2025年7月
近年では、クリニックを探す際の情報収集手段としてインターネットが主流となり、クリニックを選ぶ際には、スマートフォンやパソコンで検索してクリニックの雰囲気や診療内容をチェックしてから来院を決めるという流れが当たり前になっています。特に初診の患者にとって、ホームページはクリニックの“顔”とも言える存在となり、第一印象を左右するだけでなく、来院のきっかけを作る強力な集患ツールにもなるのです。
しかし、ホームページ制作には思わぬ落とし穴もあります。いくらデザインが素敵でも、SEO対策や情報の分かりやすさ、更新のしやすさなど、実際の運用面まで考慮しなければ、せっかくのホームページが機能しないこともあります。
本記事では、クリニックにとってホームページがなぜ重要なのかを解説するとともに、制作時によくある失敗例や外注時の注意点、そして集患につながるホームページ制作のポイントまで、実践的な視点で詳しくご紹介します。
● 中小企業の方、個人事業主さま必見!お役立ち資料無料ダウンロード

デジタルマーケティング手法が丸わかり!あなたの店舗・企業の集客に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます
クリニックにとってホームページが重要な理由
多くの人がクリニックの検索にインターネットを利用する現代では、ホームページは「信頼構築と集患のための最前線の窓口」となります。
ここからはクリニックにとってホームページが重要な理由について解説していきます。
クリニックの第一印象を決定づけるデジタル受付になるため
前述のように、ホームページは患者とクリニックの最初の接点であり、いわば「デジタル受付」のような存在です。
そのため、例えば診療時間やアクセス情報がすぐに見つかるか、院内の写真やスタッフの紹介が掲載されているかなど、ホームページの内容によって「このクリニックは丁寧で安心できそう」といった印象が決まることも多くあります。
逆に、情報が古かったりスマートフォンで見づらかったりすると、不安を感じて別のクリニックを探してしまうかもしれません。このように、第一印象を意識したホームページ制作がとても重要なのです。
強力な集患ツールとして活用できるため
ホームページは、地域の患者にクリニックの存在を知ってもらい、来院につなげるための強力な集患ツールにもなります。
例えば、「○○市 内科」などの検索結果で上位表示されるようにしっかりとSEO対策を行えば、新規患者にもアプローチが可能です。また、診療内容や予約方法をわかりやすく掲載することで、安心感を与え、来院のハードルを下げることができます。
さらにホームページ内に、よくある質問(FAQ)やWeb予約機能を設けることで、受付時間外にクリニックを探している患者も逃すことなく集患につなげることができます。受付時間内の電話対応や受付業務の負担の軽減にもなるので、集患だけでなく業務効率化のサポートにもつながると言えるでしょう。
クリニックのホームページ制作でありがちな5つの失敗例
ではここからは、実際にホームページを作るにあたって陥りがちな失敗例を5つご紹介します。
見た目は綺麗でもSEO対策が十分にできていない
見た目が美しく、写真やデザインにこだわったホームページでも、SEO対策が不十分だと検索結果に表示されにくく、集患にはつながりません。ターゲットにクリニックを知ってもらうためにも、「地域名+診療科名」などの重要キーワードをページ内に自然に盛り込んだり、適切なタイトルタグやメタディスクリプションを設定したりなどのSEO対策が必要です。
例えば、「○○市 内科」などといった検索キーワードがページ内に自然に含まれていないと、検索エンジンにそのページの内容を正しく評価してもらえず、検索順位が上がりません。結果として、どんなに見た目が良くても、患者に見つけてもらえないホームページになってしまうのです。
利用者が求める情報にアクセスしにくい
クリニックのホームページを作る上で重要視しなければならないのが、患者目線に立つということです。いくらおしゃれで凝ったデザインでも、ホームページを訪れた利用者が求める情報にうまくたどり着けなければ、あきらめて別のクリニックを探してしまうかもしれません。
このため、診療時間や診療内容、予約方法やアクセスなどの患者が求める情報はすぐに目につく場所にわかりやすく掲載することが大切です。また、問い合わせやWeb予約などのボタンを目立つ位置に設置して、クリニックへのコンタクトを取りやすくする工夫も必要です。
他院と比較した際に自院だけの価値がわかりにくい
近年では、患者はインターネットで簡単に多くの情報を収集することができるようになりました。しかし、多くのクリニックが似たようなデザインや表現を使っているため、患者にとって「どこを選べばいいのか」が分かりにくくなりがちです。
そのため、自院ならではの強みや特徴を明確に打ち出さないと、他院との違いが伝わらず、選ばれる理由がなくなってしまいます。選ばれるクリニックになるためには、専門性、診療方針、医師の人柄などの自院の強みや特徴をホームページでもわかりやすく伝える工夫が必要です。
ホームページの情報更新に手間がかかる仕様になっている
クリニックのホームページでは、診療時間の変更や休診日のお知らせ、予防接種の案内など、患者にとって重要な情報をタイムリーに発信する必要があります。しかし、更新作業に専門知識が必要だったり、外部業者への依頼が前提となっている仕様だったりすると院内スタッフが気軽に対応することが難しくなり、情報が古いまま放置されるという状況に陥りかねません。
その結果、患者が誤った情報をもとに来院してしまうなどのトラブルが起こり、信頼を損なう原因になってしまう可能性もあるのです。
更新に手間がかかると日々の運用が負担となり、結果として患者にとって役に立たないホームページになってしまいます。そうならないために、制作の段階で、誰でも簡単に更新できる設計や定期的な運用サポートの仕組み作りをしておきましょう。
医療広告ガイドラインに抵触している
クリニックのホームページ制作でありがちな失敗例の一つに、厚生労働省の定める医療広告ガイドラインに抵触してしまうということがあります。違反した場合、行政指導や処分の対象となってしまいます。
禁止されている表現には以下のようなものがあります。
- 虚偽広告
- 医学的根拠のない効果や安全性の断言
- 比較優良広告
- 他院より優れていると示す表現
- 誇大広告
- 実績や効果を過剰に強調する表現
- 体験談やビフォーアフター写真
- 限定解除の条件を満たさない場合は掲載不可
例えば、「地域No.1」「絶対安全」などの表現を安易に使うと、医療広告ガイドラインに抵触する可能性があります 。特に、自由診療に関する情報やビフォーアフター写真、体験談の掲載には厳しいルールがあり、限定解除要件を満たしていない場合は違反と判断されることもあるので注意が必要です。
これらに違反すると、行政指導や罰則の対象になるだけでなく、患者からの信頼を失うリスクもあります。クリニックのホームページ制作時には、ガイドラインを正しく理解し、法令に沿った情報発信を行うことが不可欠です。
参照:厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
具体的な事例は厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」に記載。
ホームページ制作を外注する場合に確認しておきたい注意点
クリニックのホームページ制作は、単にデザインや機能性だけでなく、医療機関としての信頼性や法的な配慮も含めて注意しなければならないことが多くあります。このため、自作するのも手間がかかるため、外注するケースも多くなるでしょう。
ここでは、外注前に確認しておきたいポイントを整理し、安心して制作を進めるための注意点をご紹介します。外注先に悩んでいる方は、以下の3点で比較して外注業者を検討してみてください。
月額・初期費用は相場と比較して高すぎないか
ホームページ制作の外注費用は委託先の制作会社によって異なるため、複数社の見積もりを比較することが重要です。初期費用、公開後の運用費用それぞれについて、相場と比較して高すぎないか、どこまでのサービスが費用内に含まれるのかなど、事前にしっかりと確認しておきましょう。
しかし、医療業界は制作時のルールが厳しいため、医療系特化の制作会社だと多少金額が上がる可能性はあります。その分ガイドラインの順守が約束されているなどのメリットはありますが、医療特化の制作会社と業界問わず対応している制作会社のどちらも検討して判断するのがおすすめです。
【関連記事】
ホームページの作成費用の相場がわからない方は、こちらの記事も併せて確認しましょう。
ホームページ作成費用を決める3つのポイント!サイト別相場も
契約期間の縛りがないか
ホームページ制作や運用を外注する際、契約期間に関する条件は見落とされがちですが、長期契約が条件となっていたり、途中解約に高額な違約金が発生したりするケースもあるため、契約更新のタイミングや自動更新の有無、解約の申し出期限などについても事前に確認が必要です。
必ず契約前に確認し、将来的に柔軟な見直しができるかどうかもチェックしておきましょう。
原稿作成の手間はどれくらいかかるのか
クリニックのホームページ制作では、診療内容や院長紹介、アクセス情報などの原稿をクリニック側で用意する必要がある場合があります。制作会社によっては文章作成をサポートしてくれるところもありますが、基本的な情報提供や初稿の準備はクリニック側が準備しなければならないケースもあるのです。
事前にどの範囲まで原稿作成が必要なのか、写真や文章の準備にどれくらい時間がかかるのかを確認しておくことも、その後のホームページ制作のスムーズな進捗のために必要と言えます。
集患できるクリニックのホームページ制作のポイント
集患できるホームページを作るには、さまざまな工夫や対策が必要です。
患者が安心して来院を決められるような情報設計、検索で見つけてもらえる工夫、そして公開後の運用までを意識することが、成果につながるホームページ制作の鍵となります。
ここからは、集患できるクリニックのホームページを作るために押さえておきたい具体的なポイントを4つの観点からご紹介します。
患者目線で情報の掲載場所・掲載方法を考える
クリニックのホームページ制作では、診療内容やアクセス方法、予約手順など、患者が知りたい情報を見つけやすく、わかりやすい場所に配置することが重要です。
例えば、初めて来院する方が不安に感じやすい「診療の流れ」や「持ち物」は、トップページの分かりやすい場所に掲載することで、初診の方にも安心感を与えることができます。「初めての方へ」というページを作って、初診の方への注意事項などをまとめて掲載するのもよいでしょう。
診療時間や休診日も、カレンダー形式や色分けで視認性を高めると親切です。アクセス情報には、地図だけでなく「最寄り駅から徒歩○分」「駐車場の有無」など、実際の移動をイメージできる情報も記載しておくと安心感が増します。また、クリニックの写真や、院長の写真などを掲載することでクリニックの雰囲気を伝えることができ、初めて来院することへの不安を和らげることもできるでしょう。
適切な検索ワードを設定してSEO対策をする
集客できるホームページ制作において、SEO対策は欠かすことのできない重要なポイントです。患者が検索する言葉を意識したSEO対策が、集患につながります。
例えば「地域名+診療科目(例:△△市 小児科)」「地域名+疾患名(例:〇〇市 高血圧)」など、患者が実際に使う検索ワードを意識してホームページ内に自然に盛り込むことが重要です。さらに、「土日診療」「予約不要」「女性医師在籍」などのクリニックの特徴もキーワードとして活用することで、顕在層の検索結果画面での露出を高めて来院につながりやすくすることも効果的です。
また、キーワード設定とはやや離れますが、スマートフォンでの閲覧に対応したレスポンシブデザインにすることやページ表示の速さを維持すること、定期的な情報更新もSEO対策として有効となります。
【関連記事】
基本的なSEO対策について詳しく知りたい人は、以下の記事がおすすめです。
内部SEO対策の基礎知識
PV数や問い合わせ数の推移を計測して正しく成果を確認する
ホームページは公開がゴールではありません。集患できるホームページにするためには、公開後の運用をしっかりとしていくことも重要になります。
効果的にホームページを運用するには、定期的なアクセス解析と改善が必要であり、分析にはGoogleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを活用することが一般的です。このツールでPV(ページビュー)数や問い合わせ件数の推移を定期的に計測することで、どのコンテンツが集患に貢献しているかを分析できます。
例えば、「よく見られているのに、問い合わせにつながっていないページ」は問い合わせへの導線を改善する必要があります。改善後の数値も注視し、「予約ページへの導線が強化された後に問い合わせが△%から〇%に増加した」というように成果を数値で確認しましょう。継続的な分析と改善をすることで、患者にとって使いやすく、クリニックにとって集患できるホームページを運用できるのです。
【関連記事】
Googleアナリティクスの具体的な使い方を知りたい方は、こちらの記事も併せて確認しましょう。
Googleアナリティクスとは?
法改正も含めてホームページの情報更新を怠らない
ホームページの情報は、常に最新の情報にしておくことが重要です。掲載されている情報が古かったり、最終更新日がかなり以前のままだったりすると、ホームページを訪れた人に不安感を与えてしまいます。
特に診療時間や休診日などの情報は常に最新の情報に更新するようにしましょう。ブログ機能などを活用して、最新のお知らせや季節性・流行性疾患に関する情報を発信するのも効果的です。
また、医療広告ガイドラインをはじめとする法改正などにも迅速に対応する必要があります。更新をしていないことでペナルティとなるケースもあるので、常にアンテナを建てて更新できる状態にしておきましょう。
【関連記事】
ホームページの掲載義務事項が変更となった「診療報酬改定」について、具体的な修正点を以下で解説しています。
令和6年度診療報酬改定によるホームページの修正点は?掲示義務事項を解説
クリニックのホームページは、単なる情報発信の場ではなく、患者との信頼関係を築き、来院につなげるために重要なツールです。見た目の美しさだけでなく、患者目線の情報設計、SEO対策、運用のしやすさ、そして法令遵守までを意識することで、失敗を防ぎ、成果につながるホームページが実現できます。
今回ご紹介したポイントを参考に、クリニックの魅力がしっかりと伝わる集患力のあるホームページ作りをめざしましょう。
● 中小企業の方、個人事業主さま必見!お役立ち資料無料ダウンロード

デジタルマーケティング手法が丸わかり!あなたの店舗・企業の集客に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます
NTTタウンページでは、ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」をご提供しています。
2019年のサービス提供開始以降、累計45,000件を超えるホームページを制作・運用し、個人事業主、中堅・中小企業をはじめとした多くのビジネスオーナーさまにご利用いただいてきました(2025年3月現在)。
これまで培ってきたNTTグループの知見とノウハウを活かして、多種多様なサービスと充実のサポート体制で、忙しいビジネスオーナーさまのホームページ制作から公開後の運用に至るまで、責任を持ってサポートいたします。

ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」の特長
特長①
ホームページ制作・運用はNTTグループの専門スタッフがフルサポート!
特長②
さまざまな目的のホームぺージ制作に対応、デザインも洗練!
特長③
ネットショップ・予約機能など、ホームページでの成約に導く充実機能多数!
ホームページは"制作して終わり"ではなく、その後の集客や売上アップなど目的の「成果」につなげてこそ価値があります!
「インターネット・Webが苦手なのでサポートしてほしい…」
「競合に”勝てる”ホームページをめざしたい」
など、当社は全てのビジネスオーナーさまのホームページ活用に関するお悩み・課題に寄り添い支えます。
ぜひ、あなたのホームページの全てをお任せください!
この記事の著者

NTTタウンページ Webマーケティングチーム
全員がウェブ解析士資格取得。同社にてWebマーケティングの他、ホームページ制作・営業・CSM(カスタマーサクセスマネジメント)など、幅広い業務経験を積んだメンバーにより構成され、ビジネスオーナーさまのホームページ制作・運用やWebマーケティングに役立つ情報を発信しています。
・Googleアナリティクスは、Google LLCの登録商標または商標です。
ホームページ制作の基礎知識に関連する記事